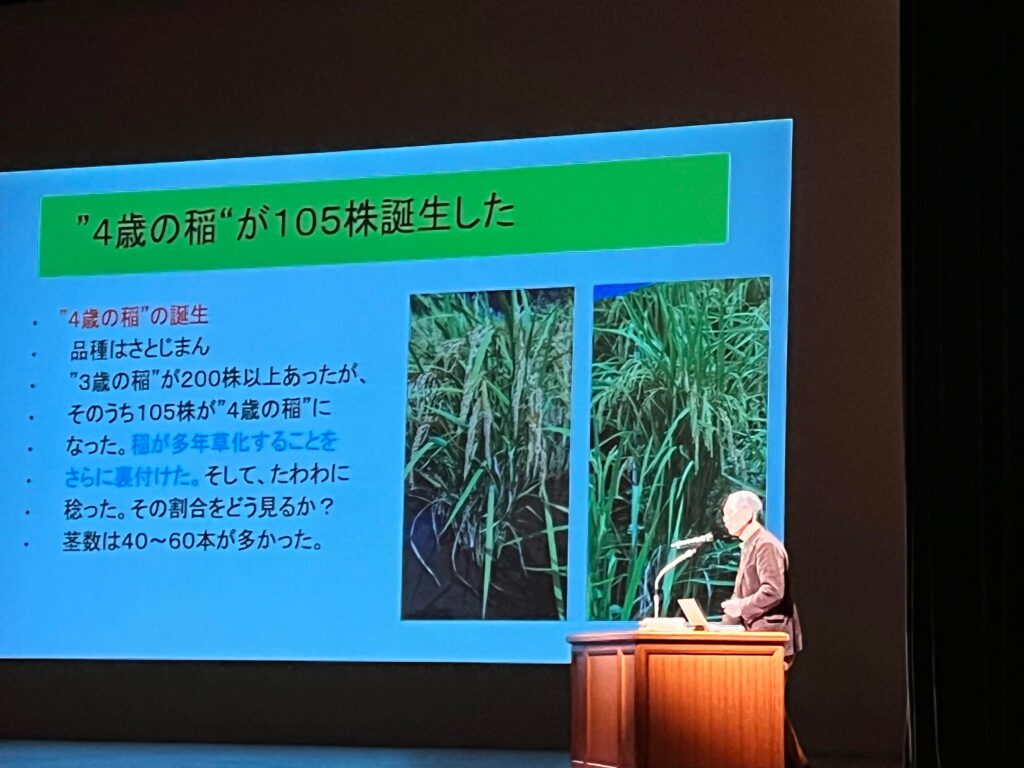畑では時々スズメバチを見かけます。その大きさや優れた飛翔能力、そして強力な歯から察せられるのは、虫の名ハンターだろう、きっとたくさん虫を獲ってくれているだろうということです。
今日は大根の葉にいたので、
「ちょっと手に乗ってちょうだい」
と頼んだところ、始めは逃げていましたが、
先回りして掌を広げていたら、ちゃんと乗ってくれました。
近くで見ると可愛いもんです。
触手をせわしく動かしなら、よちよち歩きをして、私の手が気に入ったのか、中々離れてくれませんでした。
でも、そんなに遊んでいる時間がなかったので、また大根の葉っぱに乗り移ってもらいました。
スズメバチは、民放テレビで毎年夏になると全面的に悪者扱いされて、スズメバチハンターに一網打尽にされる特集が組まれています。それらは不必要なまでに恐怖心を煽っていて、
スズメバチに対するひどい誤解を生んでいると思います。
子供のころ、よく農家の軒下にスズメバチの丸い大きな巣があって、
「かっこいいなあ!」と憧れました。玄関にスズメバチの巣を飾っている家もありましたね。
農家はスズメバチの役割を良く知っていたから、軒下に巣を作られても決して除去したりしなかったんですね。
そして、もちろん敵意も恐怖心も持たなかったら、スズメバチが農家を刺すなんてこともなかったんだと思います。
私も毎年のようにスズメバチと遭遇しますが、いまだに一度も刺されたことはありません。
ただ、警告されることは少なからずあります。耳すれすれにすごい速さでブーンと飛んできたときはきっと警告しているんだと思います。そばに巣があるか、何か近づかれては困ることがあるんでしょうね。そういう時は周りをよく注意して見て、スズメバチの巣がないか、彼らの邪魔をしていないか気を付けます。
スズメバチの針は毒があって、刺されるととても痛いそうですね。しかも、2度刺されると死ぬと聞きます。そんな恐ろしいハチなのかと思ってしまいがちです。しかし、そう言う人ってどういう人なんだろうかと、逆に知りたくなります。街中を歩くのと同じような気分で歩いていれば刺されるなんてことはないように思うのですが。
なお、写真はコガタスズメバチです。性格は穏やかなようですが、毒性の強い針を持っているそうです。
でも、きっとスズメバチからすれば、今の人間の方が何倍も恐ろしい毒を持っていると思うんじゃないでしょうか?