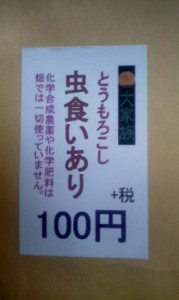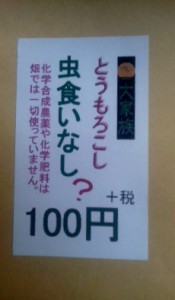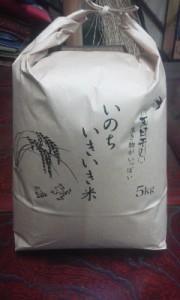自然耕塾第2回目は、稲の種まきと苗箱の苗代での設置を行いました。最初に機械で種まきをして、次に手で播きました。 「毎年、手播きのほうは、播く人によって発芽率が良かったり、悪かったり、大きな差がでますからね!」とちょっと脅して(?)、「これで大丈夫だろうかという不安や、悲しい想いで播くと発芽率が悪くなって、生育にも影響がでるので、平常心で播いてください。」 それを聞いて、塾生は無言で、真剣に種を播いていました。 こんな感じになります。
薄播きで、人間の居住空間に譬えると、5LDKぐらいにゆったりとしています。そこで太陽の光をたっぷりを浴びて、寒さの中で鍛えられて、逞しい苗に育ちます。 その上に土をかけて完成です。午後は、その苗箱を苗代に設置しました。
そのあとで、講義に夢中になっていたら、4時半になってしまっていました。塾生のみなさん、遅くまでお疲れ様でした。
小川