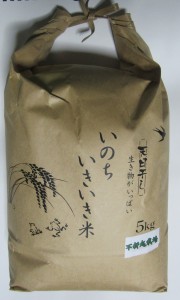丁度1か月前から始まったトウモロコシの収穫がほぼ終わりました。
その間ずっとハクビシンとトウモロコシを分かち合ってきました。その結果は
次の通りです。
販売用の収穫総数 614本
ハクビシン用 89本
合計 703本
ハクビシンが勝手にもいで食べたもの総数 10本程度
ハクビシン用には虫食いのものや小さくて売り物にならない物をもいで、全部皮をむいて土に差したり、土の上に置いたりしてきました。
その9割ぐらいをハクビシンは食べてくれました。ハクビシンが勝手にもいで食べたものも小さめのものがほとんどでした。食べた量から判断して、食べに来ているハクビシンは多分1匹だけだと思います。こうして、ハクビシンの協力によって販売に向いたトウモロコシはほぼ100%収穫できたと言っていいと思います。
畑では毎回必ず畑を浄めてから、主の神様に感謝の祈りを捧げ、最後の一本の収穫が終わるまでハクビシンとの分かち合いを続けさせていただけますようにと、祈りを捧げました。
時々は、日本人が自分勝手にハクビシンを台湾や中国から日本に連れてきて、用がなくなったら、野山に捨ててしまったことと、いまだにそうしていることを深くお詫びしました。そして、毎回ハクビシンのためのトウモロコシを用意した後で、ハクビシンに向けて頭の中でハクビシンに語りかけました。つまり念じました。販売用のトウモロコシを荒らさないで残しておいてくれてありがとう、今日もトウモロコシを用意したので食べてください、足りなかったら、勝手にもいでたべてください、と。
今年でハクビシンとのトウモロコシの分かち合いは、3年目になりますが、初めから終わりまで非常に順調に行きました。ハクビシンはほぼ完全に私に協力してくれました。こういう言葉が当たっているかどうかわかりませんが、私もハクビシンもお互いを信頼し合っていると思います。また互いにその信頼に応えるように努めてきました。だから、そこには友情に近いものが生まれていると思います。まだ一度も会ったことはありませんが。
このような経験から皆さんにお伝えしたいことは、次のようなことです。去年とほとんど重複しますが、大切なことなので、また書かせていただきます。
(1)ハクビシンについて
- ハクビシンが畑を荒らす理由は、日本人に怒りを抱いているからです。勝手に日本に連れてきて、不要になったら、ペットに飽きたら、野山にポイ捨て同然に放棄した自己中心的で、身勝手な行動に憤りを感じているからです。
- ハクビシンは栽培者が考えていることを全部知っています。心が読めるのです。(mind-reading)それで、日本人に復讐するために、栽培者が収穫しようと思った、その時を狙って作物を荒らすのです。
- 私たち日本人が天地創造の神様にハクビシンに対して行ったむごい仕打ちをお詫びして、ハクビシンにもお詫びして、ハクビシンに仲良くしていこうと語りかければ、ハクビシンは私たちを許すかどうかはわかりませんが、仲良くする気持ちは持っています。そのことがこの3年間の私の実践で裏付けられたことです。
(2)天地創造神に対するお詫び
自然の背後には天地創造神が決めた厳粛なる掟があって、人も 動物も本来はそれを守らなければいけないようになっていると感じます。それを真っ先に犯したのが日本人です。つまり、日本人には生態系を撹乱した罪があるのだと思います。これは私の信仰から出た想い込みではなくて、〈厳粛なる掟〉がそうなっているということです。ですから、まずは私たち日本人が天地創造の神様に、その掟を破った罪に対して、真剣にお詫びをする必要があると思います。そして、同時にハクビシンにもお詫びをしないといけないのだと思います。そこを外しては、ハクビシンの怒りは収まらないだろうと思います。
全国的に年々獣害はひどくなっています。総被害額は500億を超えたと聞いたことがあります。その本当の原因は一体どこにあるのでしょうか。この報告書が今まで光が当たらなかった箇所に少しでも光を当てることができたなら、幸いです。