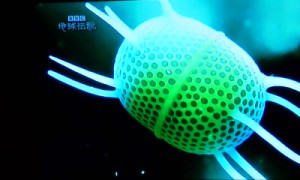21世紀、環境の世紀に相応しい農法がまだありません。
20世紀までは畑や田んぼ、あるいは果樹園の中で何をどうするかだけを考えていれば、それで済んだかもしれません。しかし、地球環境問題がここまで深刻になっている今、私たちは地球的視野に立って、地球市民として、畑は草地の自然環境として、田んぼは水辺の自然環境として、果樹園は林の自然環境としてとらえ直して、正しいかかわり方を考えていく必要があります。上手にかかわれば、そこは生物多様性のある2次的な里地里山的な自然環境として蘇ります。そして、そこで得られる自然の恵みは、生産者と消費者という垣根を取り払って、自然の恵みを分かち合い、互いの命と生活を支え合う、和やかな人的環境とすることも可能です。それは、田畑の中と同じかそれ以上に大切なことです。「和み農」はそのような考えに基づく、21世紀の農法というか、「農」に親しむ人、「農的な生活」を楽しむ人、しいては専業農家にも十分通用する、「農」の指針のたたき台です。
大勢で大いに叩き合って、21世紀に相応しい指針を作り出したいと考えています。
「和み農」では以下の8つのことを大切にしています。
1.全ての生き物と共生し、
2.環境と調和して、
3.排出ガスを最小限に抑え、
4.作物と心を通わせ、
5.資材を循環させて、
6.技能を磨き、
7.“本当に安全な作物”を作る
そして、
8.神への祈りから始める
小川