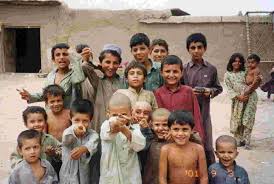(一条刈りバインダー)
稲刈で欠かせない道具が、鎌です。ただ、それでは、一人で一日やっても2畝(200㎡)ぐらいはざかけできるかどうかという感じですね。大家族の主力はバインダーです。それを使うと、どんどん刈って、束ねて、稲束をポンポンと脇に投げ出してくれます。何とも器用な機械だと、毎年感心します。おそらく日本人が考え出したのだと思いますが、こういうことを考えだした技術者には会ってお礼が言いたいですね。バインダーが描き出す幾何学模様を見るのも、稲刈りの楽しみです。
(二条刈りバインダー)
そのバインダーですが、1条刈りだと、人力20~25人分ぐらい働いてくれます。2条刈りだと40人分ぐらいの働きがあります。カッターと呼ばないで、バインダー(結束機)と呼ぶのは、なぜだろうと訝しがっていましたが、やってみるとわかります。刈るのは、簡単。でも、束ねるのに時間がかかるのです。その大変な方をばんばんやってくれるので、バインダーと呼ぶのでしょう。今では、その呼び名に納得しています。大家族ではそれに加えて人力で、はざかけをして、天日干しにします。そうやって、何とか1町歩(10,000m)まで…はこなしています。(残りはコンバインで収穫します。)バインダーがあっても、結構大変な作業です。スタッフがよくやってくれるし、市民のお手伝いもあって、4トン近くのお米を天日乾燥できています。
やはり、味の最後の仕上げはお天道様なんですね。土地の農家もそのことはよく知っていて、「コンバインじゃ、味が落ちるからなあ。」と、望地では手間のかかる方を選択する方がいまだに多いですね。大半は自家用だからだと思います。
そんなわけで、稲刈りの季節は、私にとって、「バインダー様、様。」毎回、「今日もよろしくお願いします。」と声をかけて、無事刈り終ったら、「ありがとうございました。また、明日もお願いします。」とお礼を言います。どちらも中古で、とくに2条刈りの方は20年前か30年前の代物で、ご老体ですが、良く働いてくれます。その機械はたったの3万円で買ったのですが、(新品だと80万ぐらいし)、その元の持ち主から「良く動いてるなあ。」と言ってきたので、「もっと早く壊れると思ってましたか。」と半分からかってやりました。感謝して使うと、機械でも老体にムチ打って、がんばってくれます。
小川